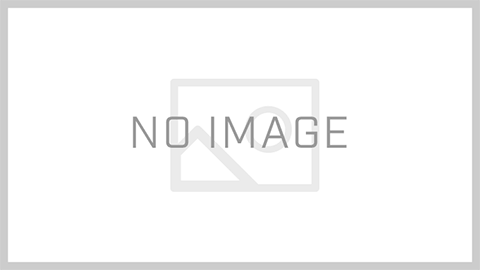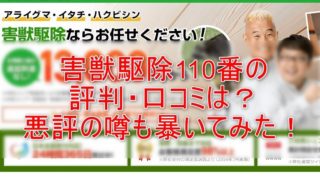白くてまん丸く、ツルツル肌がかわいいカブ。
葉はビタミンや鉄分、カルシウムが豊富で、根には胃腸の働きを助けてくれるデンプン分解酵素が多く含まれています。
生で食べればシャキシャキ、火を通せばトロ~リ。
様々な調理法で楽しめるのもカブの魅力ですね。
小カブは生育期間が40~50日と短く、簡単に栽培できるので、家庭菜園にも向いています。
そんなカブの栽培ですが、害虫に表面を食べられてしまうと、ザラザラ肌のカブになってしまいます。
しかし、ある対策をおこなえば害虫の被害を防ぐことができ、初心者のあなたでも上手に美味しいカブを作ることができますので紹介していきますね。
そこで、カブの育て方と栽培のコツを
- カブ栽培の特徴
- 実割れや害虫被害を防ぐコツ
- おすすめの品種
- 植え付け~収穫までのポイント
にわけて、説明していきたいと思います。
年間で約40種類の野菜を作り、家庭菜園歴12年の知識と経験から、初心者のあなたでもわかりやすく説明していきますね^^
栽培のコツを掴んで、丸くてきれいなカブを収穫してみましょう!
カブの栽培の特徴とコツ
カブの栽培の特徴
カブの栽培の特徴とコツをつかめば、初心者でも簡単に作ることができますよ♪
栽培難易度:★★★☆☆
分類:アブラナ科
種まき時期:4月中旬~4月下旬(春まき)、9月上旬~9月中旬(秋まき)
収穫時期:5月下旬~6月下旬(春まき)、11月上旬~2月下旬(秋まき)
発芽適温:20℃~25℃
生育適温:15~20℃
好適土壌pH:5.5~6.5
連作障害:不可。1~2年あける。
【栽培のコツ1】こまめに水やりをして実が割れないようにしよう!
カブは急激に水分を吸収すると実割れを起こしやすくなります。
そのため、ひどく乾燥させないように注意が必要です。
こまめに水やりをして、畑の水分を保つようにしましょう。
また、カブは土壌の水分が十分あるときに肥大して、まるい形に生長します。
実が細くなるのは、水不足が原因です。
【栽培のコツ2】防虫ネットでツルツルのカブを作ろう!
真っ白でツルツルの肌が持ち味のカブですが、表面がザラザラとしてしまうことがあります。
これは、アブラナ科に共通する害虫「キスジノミハムシ」の幼虫に食べられてしまうためです。
害虫を防ぐためには、防虫ネットが効果的です。
種まき後に防虫ネットをトンネル掛けし、収穫期までトンネルを外さずに栽培を続ければ、虫害を防ぐことができます。
防虫ネットはできるだけ目の細かいものを選ぶとよいでしょう。
カブのおすすめの種まき時期は9月上旬~9月中旬(秋まきの場合)
カブは高温に弱く涼しい場所を好む野菜で、春まきと秋まきができます。
春まきに比べ病害虫の発生が少ない秋まきが育てやすいでしょう。
また、春まきで種まきが早すぎると低温にあい、トウ立ちしやすくなります。
<春まき>
- 寒冷地(東北等) : 4月下旬~5月上旬
- 中間地(関東等) : 4月中旬~4月下旬
- 温暖地(四国・九州等): 4月上旬~4月中旬
<秋まき>
- 寒冷地(東北等) : 8月下旬~9月上旬
- 中間地(関東等) : 9月上旬~9月中旬
- 温暖地(四国・九州等): 9月中旬~9月下旬
カブのおすすめの品種は金町小かぶ、玉波、聖護院
カブには大きく分けて、直径5~6cmの小カブ、10cm前後の中カブ、15cmの大カブがあります。
また、形や色が違う品種もあります。
まずは生育期間が一番短い小カブを栽培してみて、中カブ、大カブ、少し変わった品種へとチャレンジしてみることをオススメします。
金町小かぶ (小カブ)
関東地方を中心に栽培されている代表的な小カブです。
肉質はやわらかく、甘みがあります。
茎葉もやわらかく、漬物や油炒めにして美味しくいただけます。
玉波 (中カブ)
暑さ、寒さに強く耐病性があります。
す入りが遅く、変形や実割れも少ないので初心者にも育てやすく人気のある品種です。
聖護院 (大カブ)
京都名産の「千枚漬け」に使われている大カブ。
なめらかでツヤのある肌が特徴で、甘みが強く肉質もやわらかいカブです。
[quads id=2]
カブの育て方と栽培のポイント
手順1.水はけと水持ちの良い土作りをしよう!
畝を高くし、水はけと水持ちをよくすることが土作りのポイントです。
- 種まきの2周間前に苦土石灰を1㎡あたり100gまき、深さ30cmまで土をよく耕しておきます。
- 土が硬かったり、土のかたまりがあるときは、よくほぐし、小石などは取り除いておきます。
- 種まきの1週間前に、1㎡あたり堆肥2gと化成肥料100gを施し、土とよく混ぜます。
- 幅60~100cm、高さ10cmの畝を立て、マルチシートを敷きます。
アブラナ科の作物であるカブには「根こぶ病」という病気が発生することがあります。
「根こぶ病」を防ぐためにも、連作をさける他、高畝にして水はけのよい土を作ることがポイントです。
手順2.5~10cm間隔で4~6粒種をまこう!
カブは移植ができないので、必ず畝に直接まきます。
- 5~10cm間隔をあけてマルチシートに穴を開け、深さ1cm程度の植え穴を掘ります。
- 1か所に4~6粒種をまき、上から軽く土をかぶせ、水をやります。
種を多めにまくことで、カブは競い合って根を伸ばすので、発芽とその後の生育がよくなります。
また、カブの種は畑に直接まくので、生長の過程で傷んだり、虫に食われたりしてうまく育たない場合もあります。
そのため、多めに種をまき生長の様子を見ながら間引いていくことで、最終的に質のよい株を残すことができるのです。
手順3.【間引き①】発芽がそろったら
間引きは一度に行わず、3回に分けます。
1回目の間引きは、発芽がそろったら行います。
混み合ったところ間引き、葉が重ならないようにします。
手順4.【間引き②】本葉が3枚になってから
2回目の間引きは、本葉3~4枚になった頃に行います。
病害虫に侵されているもの、生育が早すぎるものや遅れているものを取り除きます。
残すカブの根を痛めないように気をつけながら間引きしましょう。
手順5.【間引き③】本葉が5枚になってから
3回目の間引きは、本葉5~7枚になった頃に行います。
間引きした葉は捨てずにぜひ料理に活用してみてください。
間引き菜はやわらかく食べやすいので、漬物や炒めものにすると、よいご飯のお供になりますよ。
手順6.【間引き④・土寄せ・追肥】最終は10cm間隔にしよう!
- 小カブの場合は、最終的な株間が10cmになるように間引きをします。
- 最後の間引きが終わったら、1㎡あたり1化成肥料30~50gを施します。
- 土が硬い場合はよくほぐしてから、株元に土を寄せて、根元を軽く埋めるようにします。
しかし、土寄せをすることで日焼けを防ぎ、真っ白なカブを育てることができますよ^^
中カブの場合は20cm、大カブの場合は30cmほどの間隔で間引きしましょう。
肥料を施す場合は、マルチの下に手を入れて、株元から少し離れたところに均一にばらまきす。
カブの収穫時期と収穫方法
カブの収穫時期
カブの収穫時期は、栽培地によってかわります。
<春まき>
- 寒冷地(東北等) : 6月上旬~7月上旬
- 中間地(関東等) : 5月下旬~6月下旬
- 温暖地(四国・九州等): 5月中旬~6月中旬
<秋まき>
- 寒冷地(東北等) : 10月下旬~2月中旬
- 中間地(関東等) : 11月上旬~2月下旬
- 温暖地(四国・九州等): 11月中旬~3月上旬
大きくなったものを間引きながら収穫しよう!
カブの大きさが直径5~6cmになれば収穫できます。
品種の特性によって収穫に適した大きさは異なりますが、目安として、小カブは5cm、中カブは8~10cm、大カブは15~20cmです。
地面にカブの白い肩が出て大きくなっているものから順に、間引きながら収穫します。
収穫が遅れるとすが入ったり、実が割れる原因になるので、早めの収穫を心掛けましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、「上手なカブの育て方!連作を避け・割れない&ツルツル肌の実を収穫するコツ」を紹介してきました。
乾燥させないように水やりをし、防虫ネットで害虫を防げば、まん丸でツルツル肌のカブに育てることができますよ。
ぜひ美味しいカブの栽培にチャレンジしてみてくださいね。
【種まき時期】
栽培する地域によってかわります。
<春まき>
寒冷地(東北等) : 4月下旬~5月上旬
中間地(関東等) : 4月中旬~4月下旬
温暖地(四国・九州等): 4月上旬~4月中旬
<秋まき>
寒冷地(東北等) : 8月下旬~9月上旬
中間地(関東等) : 9月上旬~9月中旬
温暖地(四国・九州等): 9月中旬~9月下旬
【土作り】
堆肥と元肥を入れて耕し、高畝にしてマルチシートを敷きます。
【種まき】
5~10cm間隔に深さ1cmの植え穴をあけて、4~6粒種をまき、軽く土をかぶせて水を与えます。
【水やり】
土を完全に乾燥させないよう、こまめに水やりをして、実割れを防ぎます。
【間引き】
発芽がそろったら1回目、本葉3~4枚で2回目、本葉5~7枚で3回目の間引きをします。
【肥料】
最後の間引きが終わったら追肥をします。
【収穫時期】
栽培地によってかわります。
<春まき>
寒冷地(東北等) : 6月上旬~7月上旬
中間地(関東等) : 5月下旬~6月下旬
温暖地(四国・九州等): 5月中旬~6月中旬
<秋まき>
寒冷地(東北等) : 10月下旬~2月中旬
中間地(関東等) : 11月上旬~2月下旬
温暖地(四国・九州等): 11月中旬~3月上旬
【収穫】
直径5cm程度になったら収穫可能です。
す入りや実割れを避けるため、大きくなったものから順に、間引きながら収穫しましょう。